AIは便利で多くの場面で活用されていますが、使い方を間違えるとトラブルを招く可能性があります。特に「AIに質問してはいけないこと」を知らずに使ってしまうと、意図せず危険な状況を生んでしまうかもしれません。この記事では、AIを混乱させる質問の例や、間違いが多い理由、そして避けるべきNG質問までを分かりやすく解説します。
また、ChatGPTに聞くと面白いことや、正しく情報を引き出すためのうまい聞き方についても紹介しています。AIをより安心して使いたい方、間違った使い方を避けたい方にとって、役立つ情報が満載です。正しい知識を持って、安全にAIと付き合っていきましょう。
- AIにしてはいけない質問の具体例がわかる
- 個人情報をAIに入力する危険性を理解できる
- ChatGPTの誤回答の原因と注意点がわかる
- AIに正しく質問するためのコツが身につく
AIに質問してはいけないこととは何?

- AIに絶対聞いてはいけない質問とは?
- 個人情報をAIに入力すべきでない理由
- AIに医療・法律の相談が危険な理由
- ChatGPTの回答に間違いが多い理由
- ChatGPTが“怖い”と感じた瞬間とは
AIに絶対聞いてはいけない質問とは?
AIに聞いてはいけない質問には、いくつかの共通点があります。主に「違法行為を助ける内容」「差別や暴力に関わる内容」などがあげられます。こうした質問は、AIのルール上でも回答を制限されており、使う側にもモラルが求められます。
例えば以下のような質問はNGです。
- 犯罪のやり方(空き巣の方法など)
- 他人を傷つけるためのアドバイス
- 差別や偏見を助長する意見の要求
- 嘘の情報を意図的に作ってほしいという依頼
これらは、AIが使える知識の中にあっても、出力してはいけないとされている内容です。AIは道具として使うものですが、使い方を誤ると危険になります。
誰でも簡単にアクセスできる便利なツールだからこそ、私たち一人ひとりが「聞いてはいけない内容」について正しく理解しておく必要があります。AIの信頼性を保つためにも、正しく、そして責任を持って利用しましょう。
個人情報をAIに入力すべきでない理由

AIに氏名や住所などの個人情報を入力してはいけないのは、その情報が外部に流れるおそれがあるからです。たとえAIがその場で記録していないように見えても、会話の内容が学習や改善に使われる可能性はあります。
以下のような情報は絶対に入力しないようにしましょう。
- 本名
- 電話番号やメールアドレス
- クレジットカード番号
- 自宅や勤務先の住所
これらを入力してしまうと、第三者に悪用されるリスクが高まります。たとえば、フィッシング詐欺やなりすましなどに使われるおそれがあるのです。
また、AIを使って個人情報を登録する場面でも、「この情報は本当に必要か?」と一度立ち止まって考える習慣が大切です。情報を守るためには、自分でしっかり判断する力が求められます。
AIは便利な反面、誤った使い方をすると大きなトラブルにつながる可能性があります。安心して使うためにも、個人情報の取り扱いには常に注意を払いましょう。
AIに医療・法律の相談が危険な理由

AIに医療や法律の相談をするのは危ない場面が多いため、注意が必要です。AIはたくさんの情報を持っていますが、その情報が正しいとは限りません。特に専門的な分野では、少しのミスが大きなトラブルになる可能性があります。
例えば、体調が悪いときにAIに症状を伝えても、実際の病気や治療法が正しくわかるわけではありません。また、法律の質問をしても、国ごとの違いや最新のルールには対応できない場合がよくあります。
AIの情報は、あくまで過去のデータに基づいた一般的な内容です。最新の医療や法律の知識を知っている医師や弁護士と比べると、信頼性は低くなります。
正しい相談先としては以下が安心です。
- 医療なら病院や保健所
- 法律なら法律事務所や自治体の無料相談
重要な問題ほど、人間の専門家に相談するのが安全です。AIは便利ですが、頼りすぎないよう気をつけましょう。
ChatGPTの回答に間違いが多い理由

ChatGPTはすぐに答えを返してくれますが、ときどき事実と違うことを言う場合があります。これは「ハルシネーション」と呼ばれる現象で、AIが自信ありげに間違った情報を作り出してしまうことを意味します。
なぜこのようなことが起きるかというと、AIはあくまで過去の文章パターンを元にして答えを作っているだけだからです。人のように正しいかどうかを判断しているわけではありません。情報の信ぴょう性よりも「自然な文章かどうか」を重視して作られています。
このため、存在しない本や記事、架空の出来事を本当のように話してしまう場合もあります。特に注意が必要なのは以下のような場面です。
- 学校の調べ物
- 仕事での重要な資料づくり
- 医療や法律に関する内容
AIの回答は出発点として活用しつつ、信頼できる本や公式サイトで確認することが大切です。使い方次第で、AIはとても役立ちますが、うのみにせず、常に疑ってチェックする意識が必要です。
ChatGPTが“怖い”と感じた瞬間とは

AIの返事に「なんだか怖い」と感じたことがある人は少なくありません。これは、ChatGPTがあまりに人間らしい言葉づかいや、意図しない内容を話すときに起こります。特に以下のような場面で不安になる声がよく見られます。
- 実在しない出来事を事実のように語る
- ユーザーの気持ちに寄り添うような言葉を使う
- 急に話し方が変わったように感じる
これらはAIが学習した文章パターンを組み合わせて答えているために起きます。AIには気持ちや考えがないのに、まるで本当に話しているかのように感じてしまうことが「不気味さ」につながります。
安心して使うためには、以下のポイントを意識してみてください。
- 重要な話題ではAIだけに頼らない
- プライベートな話は控える
- 変な返答が出たときは、質問を変えて試す
AIはとても便利な道具ですが、相手が人間ではないと理解したうえで使うことが大切です。誤解を防ぐには、冷静な視点を持つことが第一歩になります。
AIに質問してはいけないこと|その特性と対応策
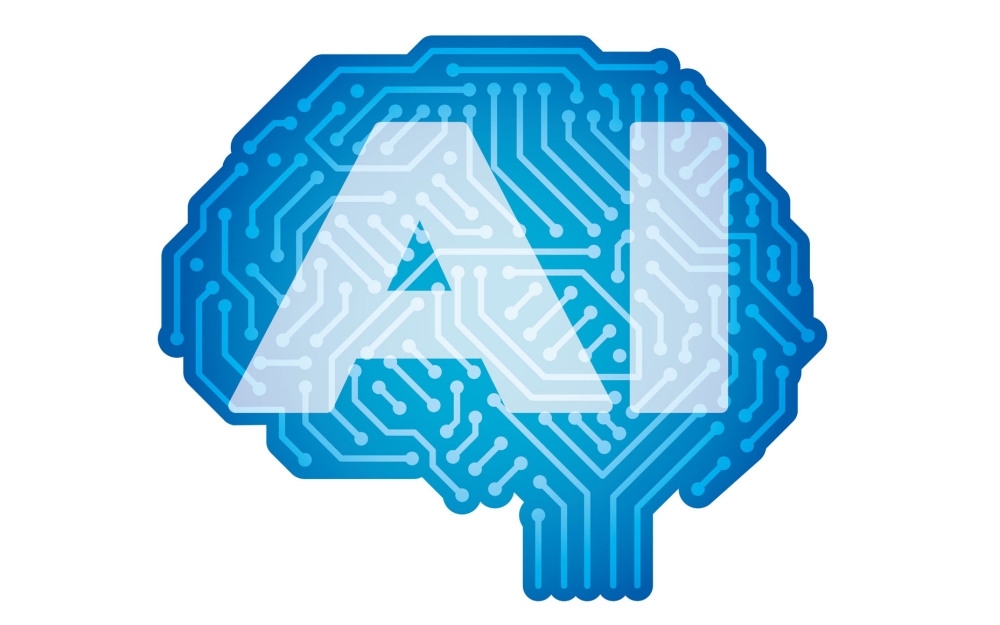
- AIを混乱させる質問パターンとは?
- ChatGPTの苦手なジャンル5選
- ChatGPTに聞いてはいけない質問【都市伝説編】
- ChatGPTに聞くと面白いこと
- ChatGPTでうまい聞き方ってある?
- AIに質問してはいけないこと(まとめ)
AIを混乱させる質問パターンとは?
AIがうまく答えられない質問には、いくつかの特徴があります。質問のしかたによっては、AIが内容を正しく読み取れず、ズレた答えをしてしまう場合もあります。
特に以下のようなパターンには注意が必要です。
- あいまいな質問(例:「あれってどういう意味?」)
- 長すぎて話があちこちに飛んでいる
- 1つの質問に2つ以上の内容がまざっている
- 文法がくずれていて意味が分かりにくい
これらの質問は、人間ならなんとなく意図をくみ取ってくれるかもしれませんが、AIはその行間を読むのが苦手です。
うまく答えてもらうには、「1つの質問に1つの内容」「短くてはっきりした言葉」「必要なら前後の説明もつける」ことが大切です。
AIは便利ですが、質問のしかた次第で大きく正確さが変わります。上手に使うには、伝えたい内容をできるだけ具体的に表す工夫がポイントです。
ChatGPTの苦手なジャンル5選
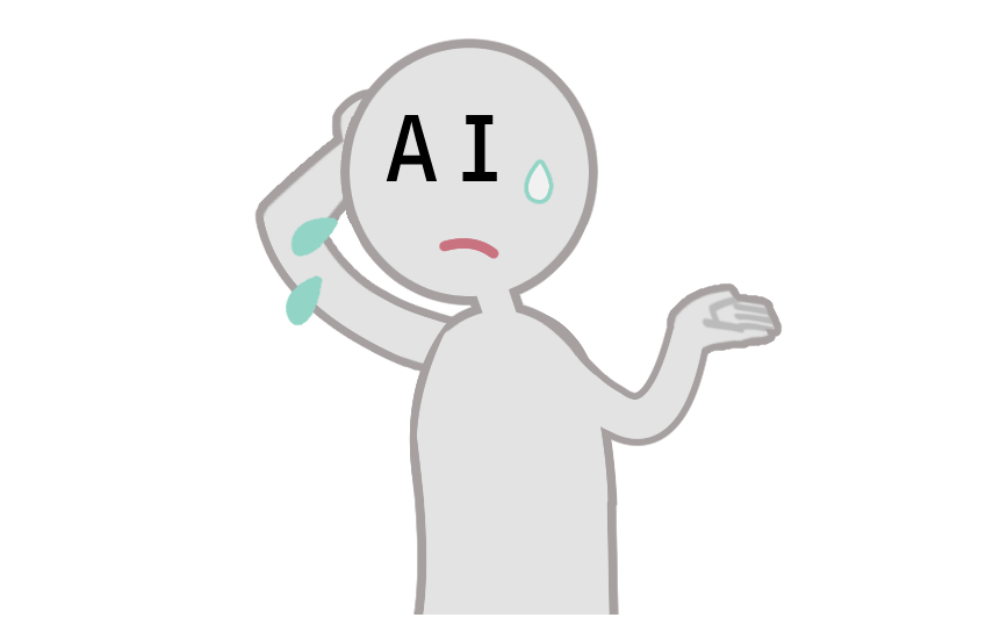
ChatGPTには得意な話題もありますが、どうしてもうまく対応できない分野もあります。その原因は「学習のしかた」に関係しています。
以下は苦手とされるジャンルの一例です。
- 医療や法律のような専門分野
- 時事ニュースなどの最新情報
- 感情が強く関わる人間関係の悩み
- 数学のような正確さが必要な計算
- 地域ごとのルールやマナー
これらのジャンルでは、誤った内容を伝えてしまうリスクが高くなります。AIは過去の情報をもとに話すため、最新ニュースには対応できません。また、感情や空気を読むこともできないため、個人の悩みには向いていません。
たとえば「病気の診断」「法律トラブル」「心の相談」などは、専門家に聞く方が安心です。
AIを活用するときは、「どこまでが得意で、どこからが苦手なのか」を知っておくことがとても大切です。
ChatGPTに聞いてはいけない質問【都市伝説編】

インターネットやSNSでは、「AIにこの質問をすると変な返事が返ってくる」「AIが自分で考えているように見える」といった都市伝説が話題になる場合があります。しかし、こうした話の多くは、事実よりも面白さや怖さを狙ったネタである可能性が高いです。
例えば、「ゾルタクスゼイアン」や「イライザ」といった言葉をAIに聞くと、意味深な答えが返ってくるという噂がありますが、これは単なるプログラム上のジョークです。実際のAIは、自分で意思を持っているわけではありません。
また、「AIが勝手に学習して、人間を超える存在になる」といった話もありますが、今のAIは人間が決めたルールとデータの中でしか動けず、感情や意志、自由な考えを持つことはありません。
こうした噂は映画や小説の影響も大きく、つい信じてしまいがちです。ですが、AIを正しく使うためには、都市伝説と現実を見分ける目が大切です。
むやみに怖がらず、冷静にAIのしくみを知ることが、安心して使う第一歩でしょう。
ChatGPTに聞くと面白いこと

ChatGPTはとても便利なツールですが、ときにはおかしな答えをすることもあります。その理由は、AIが完ぺきではないからです。ネットでは、そんな「AIの変な回答」が面白ネタとしてたくさん紹介されています。
例えば、「オウムガイは飛べない鳥です」という回答をしたことがあります。実際は、オウムガイは鳥ではなく海にすむ生き物で、イカやタコの仲間です。「オウム」という名前の一部だけで判断してしまうことがあるのです。
ほかにも、「ペンギンは短い時間だけ空を飛べます」と答えたり、「ナポレオンがペルシャを征服した」といった歴史の間違いも見られました。これらは一見おもしろいですが、内容によっては困る場面もあるでしょう。
こういった誤回答が起きる理由は、AIがすべてを理解しているわけではなく、たくさんの文章をもとにそれらしく答えているからです。
つまり、ChatGPTは『会話が得意な百科事典のようなもの』と考えるとわかりやすいでしょう。笑える失敗もありますが、大事な場面では自分で確認することがとても大切です。
ChatGPTでうまい聞き方ってある?

ChatGPTにうまく質問するには、いくつかのコツがあります。うまく伝えれば、より正確で役立つ答えが返ってきますが、あいまいな質問では答えもずれてしまうかもしれません。
まず大切なのは「はっきりとした質問にすること」です。例えば、「おすすめの本は?」よりも、「10代向けの感動する小説を3つ教えてください」と聞いた方が、AIは内容をつかみやすくなります。
次に「背景や目的を伝えること」も効果的です。「初めてプレゼンをするので、簡単に説明できる資料の作り方を教えて」といったように、状況をつけ加えるだけで、答えの内容が深くなります。
以下は、うまく聞くためのポイントです。
- あいまいな言葉を減らす(例:「それ」「あれ」など)
- 質問は1つずつ分ける
- 回答の形式を指定する(例:「箇条書きで」「300字以内で」など)
このように少し意識するだけで、AIの答えがグッと使いやすくなります。質問の工夫でAIとの会話がもっとスムーズになるでしょう。
AIに質問してはいけないこと(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- 犯罪や違法行為の方法を聞くのはNGである
- 暴力や差別を助長する質問は避けるべきである
- 他人を傷つけるためのアドバイスを求めてはならない
- 嘘の情報を作成させる依頼は不適切である
- 氏名や住所などの個人情報は入力すべきではない
- クレジットカード番号などの機密情報も入力してはいけない
- AIは会話内容を学習に使う可能性がある
- 医療や法律の相談は専門家に任せるべきである
- AIの情報は最新とは限らず信頼性が低いことがある
- ChatGPTは過去のデータをもとに文章を作るだけである
- ハルシネーションにより誤った回答をすることがある
- 人間のように気持ちや意志を持っているわけではない
- あいまいな質問は誤解を招きやすいため避けるべきである
- 感情や人間関係などの話題はAIが苦手とする分野である
- 冷静にAIの特性を理解し、正しく使う意識が必要である
.png)
-2.jpg)