読書感想文を書くのが苦手で、ChatGPTを使って読書感想文のやり方を検索している方も多いのではないでしょうか。
最近では、小学生から高校生まで幅広くAIを活用した作文が注目されており、便利なアプリやプロンプトを使えば、感想文の書き出しや構成に悩むことも減ってきました。とはいえ、AIに頼りすぎると「バレる」可能性があることも事実です。
この記事では、ChatGPTを使った感想文の正しいやり方や、バレない工夫、効果的なプロンプトの作り方、年代別の活用法まで、初めてでもわかりやすく紹介していきます。
特に、高校生の方は評価基準とのバランスにも注意が必要です。自分らしい感想文を仕上げるためのヒントを、ぜひ参考にしてください。
- ChatGPTを使った読書感想文の基本的なやり方がわかる
- AIの感想文がバレる理由とその対策を知ることができる
- 効果的なプロンプトの作り方と使い方が理解できる
- 学年別の活用法やおすすめアプリを知ることができる
ChatGPTを活用した読書感想文のやり方と注意点
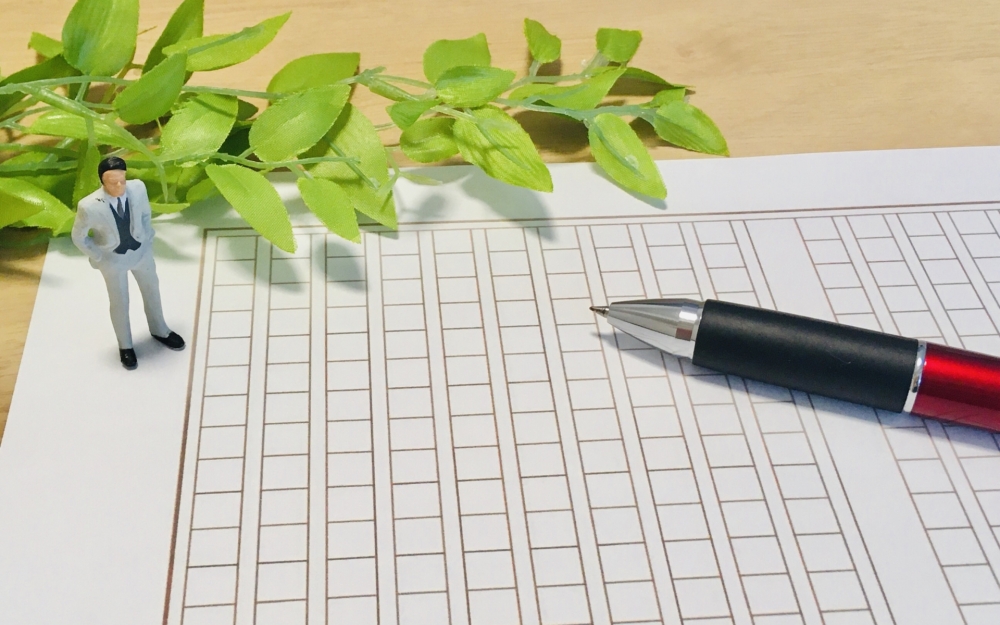
- ChatGPTで感想文を書くメリットとデメリット
- プロンプトの作り方
- AIで作成した読書感想文がバレる理由
- AIで作成した読書感想文がバレない方法5選
- AI感想文を“自分の言葉”に変える方法
ChatGPTで感想文を書くメリットとデメリット
ChatGPTで読書感想文を書くのは、時代に合った新しい方法として注目されています。ただし、その活用にはメリットとデメリット、そして守るべきルールがあります。
まず、ChatGPTを使うメリットは以下のとおりです。
- 読書感想文が苦手な人でも、書き出しや構成を作る手助けになる
- 言葉の表現方法や言い回しのヒントをもらえる
- 文章の直しや言葉の言いかえを短時間で行える
作文に対して苦手意識がある人にとって、ChatGPTは強い味方になります。特に、作文の構成を学ぶうえでの「お手本」として使う人も増えています。
一方、デメリットや注意点もあります。
- AIにまかせきりになると、自分の意見がなくなってしまう
- 自分で書いたものではないと判断されるリスクがある
- 内容に間違いや思いちがいが含まれていることもある
たとえAIの文章であっても、そのまま提出するのは不正と見なされる場合があります。また、学校によってはAIの使用自体が禁止されている場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
最後に、倫理的な面でも大切なポイントがあります。
それは「AIを使ったとしても、自分の考えを大切にする」ということです。感想文は、作品をどう感じたかを表す大切な表現です。AIはそのヒントをくれるだけで、気持ちまで書いてくれるわけではありません。
このように考えると、ChatGPTは使い方しだいで良い相棒になります。ただし、使いすぎには注意し、自分の言葉で書く意識を忘れないようにしましょう。
プロンプトの作り方

読書感想文をうまく書くためには、「どんなことを聞くか」がとても大切です。ChatGPTに正しく質問(=プロンプト)をすれば、自分の考えをうまく言葉にする手助けをしてくれます。
ここでは、感想文を作るための効果的なプロンプトを紹介します。
【おすすめプロンプト例】
- 「『〇〇(本の名前)』のかんたんなあらすじを200字で教えてください」
- 「この本の中で一番印象に残るシーンと、その理由を説明してください」
- 「この作品のテーマを中学生向けに分かりやすく教えてください」
- 「主人公の気持ちの変化について、3つの場面を使って説明してください」
これらの質問は、ただあらすじを聞くのではなく、自分の感想につなげやすい内容になっています。
また、以下のような感想文の構成を意識したプロンプトを使うと、よりスムーズに文章が作れます。
| 感想文のパート | プロンプト例 |
|---|---|
| はじめ | 「この本を読もうと思ったきっかけは?」 |
| なか | 「印象に残ったシーンは?その理由は?」 |
| おわり | 「この本を読んで、自分が考えたことは?」 |
さらに、ChatGPTに「中学生が書いたように」や「400字でまとめて」など、条件をつけることで、より自分に合った答えが得られやすくなります。
ただし、注意すべきポイントもあります。AIにまかせすぎると、自分らしさが消えてしまう可能性があります。答えをもらった後は、自分なりに言葉を直したり、体験とつなげたりして工夫しましょう。
良いプロンプトを使えば、感想文のアイデアを広げる大きなヒントになります。上手に使って、自分らしい感想文を作っていきましょう。
AIで作成した読書感想文がバレる理由
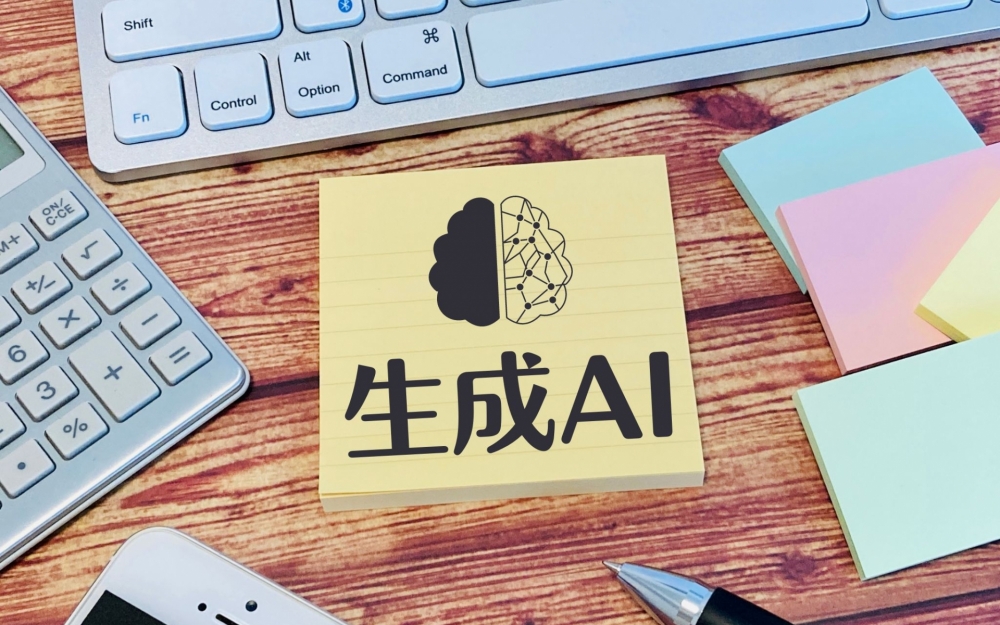
AIで作った感想文は便利ですが、バレてしまう場合があります。先生たちは意外と細かいところまで見ているので、注意が必要です。
まず、AI感想文がバレる主な理由は次の通りです。
- 表現がかたすぎて、自分の言葉に聞こえない
- あらすじばかりで、自分の気持ちが書かれていない
- 他の生徒と感想がそっくりになる
- 難しい言葉を使いすぎて、不自然に感じられる
こういった特徴は、普段の作文とのちがいからすぐに分かってしまうようです。
実際にバレた例としては、次のようなケースがあります。
- AIを使った他の生徒と同じような書き出しで感想文を提出した
- 本に出てくるキャラクターの名前を間違って書いていた
- 書いた本人が内容を説明できなかったため、先生に不審がられた
また、AIの使い方を工夫せずに出力された文章をそのまま書き写すと、全体がきれいすぎて「作られた感じ」が強く出てしまいます。
学校によっては、AIを使うだけで注意される場合もあります。そのため、使い方を間違えると成績に影響することも考えられます。
AIは便利でも、「自分らしい」文章でなければバレる可能性が高いということです。表現の参考にはなっても、まるごと使うのはリスクが大きいでしょう。
AIで作成した読書感想文がバレない方法5選

ChatGPTで感想文を書くとき、少しの工夫で自然な文章に近づけることができます。ここでは、AIっぽさをなくすための5つのテクニックを紹介します。
1. 口調を自分のものに変える
ChatGPTはきれいな言葉を使いますが、それだけだと不自然です。「〜でした」「〜だと思う」など、自分がいつも使う話し方に直してみましょう
2. 難しい言葉を言いかえる
AIは「感銘」「示唆」など難しい言葉を使いがちです。中学生らしく「心に残った」「考えさせられた」など、やさしい表現に変えると自然です。
3. 体験を入れて書き直す
感想文に、自分の体験を入れるとオリジナリティが出ます。たとえば、「友達とのけんかを思い出した」など、感じたことと結びつけることで説得力が増します。
4. 書き出しと終わりは自分で作る
AIに全部まかせると、「この本は〜」という似た書き出しになりやすいです。はじめとおわりは、自分の言葉で工夫しましょう。
5. 音読して違和感をチェック
書き終えたら声に出して読んでみましょう。自分の言葉に聞こえないところは書きなおすと、より自然な文章になります。
このように工夫すれば、AIを使ってもバレにくく、自分らしい感想文に仕上げることができます。大事なのは、「ヒントに使う」ことです。全部まかせず、自分の言葉を大切にしましょう
AI感想文を“自分の言葉”に変える方法

ChatGPTを使って感想文を作ったとき、そのまま提出するのはやめましょう。自然な文章にするには、自分らしい言葉に書きなおすことが大切です。ここでは、AIの文章を「自分の言葉」に変える方法を紹介します。
まず、AIらしい表現の特徴を知ることがポイントです。
- むずかしい漢字や言葉が多い
- すごく整った言い方で、かたすぎる印象になる
- 感情の動きが見えにくい
これらを避けるには、次の手順を使ってみてください。
ChatGPTが「感銘を受けました」と書いていたら、「心に残った」と変えてみましょう。ふだん話す言葉を使うだけでぐっと自然になります。
たとえば、「王子の決断に感動した」と書いてあれば、「その場面を読んで、自分ならどうするかを考えた」など、自分の考えを少し加えましょう。
「王子が大切なものに気づいた」とあったら、「私も友達とケンカして、あとから大切さに気づいた」とつなげてみてください。リアルな話になると、説得力が出ます。
文末が全部「〜です」「〜ます」だと読みにくくなります。「〜でしょう」「〜でした」「〜しません」などをまぜて、リズムよく整えましょう。
このようにして書きなおせば、AIの力を使いながらも「あなたの感想文」に変えることができます。大切なのは、書かれた内容を「自分が本当に思ったように」書き直すことです。コツをつかめば、だんだん楽しくなるでしょう。
ChatGPTで読書感想文を作成|世代別のやり方と活用法
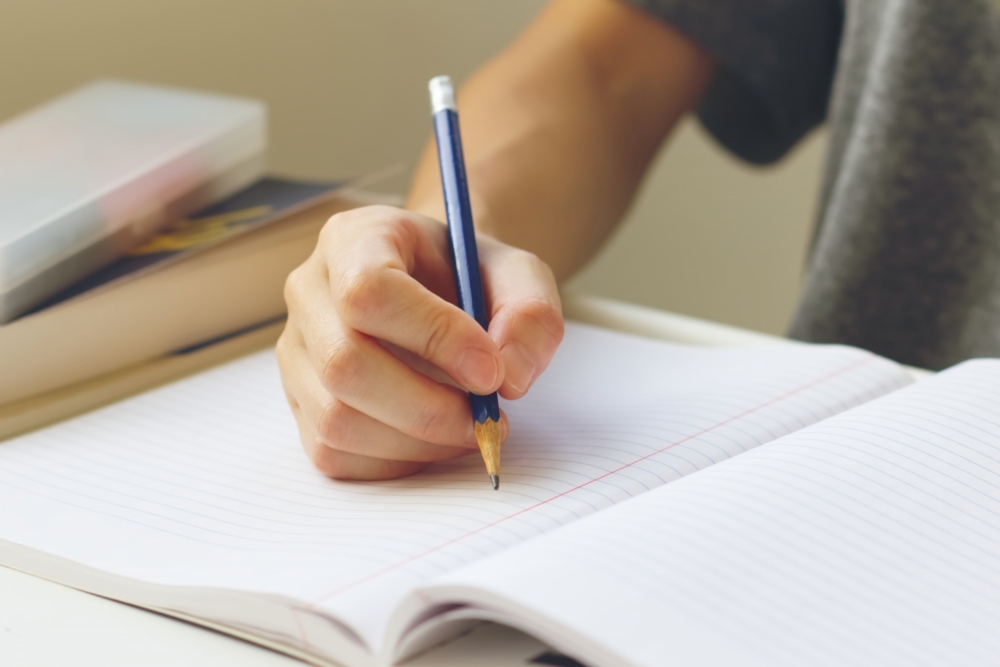
- AIアプリを比較
- 小学生向け|ChatGPTを活用した読書感想文の始め方
- 中学生向け|ChatGPT活用アイデア
- 高校生が気をつけたいChatGPTの使い方と落とし穴
- ChatGPTを活用した読書感想文のやり方と注意点(まとめ)
AIアプリを比較
読書感想文を作るときに使えるアプリやサービスは、いくつかあります。ここでは「ChatGPTを使えるもの」「使い方がかんたん」「こどもにも安心して使えるか」という3つのポイントで比べてみましょう。
| アプリ・サービス名 | 特長 | ChatGPT対応 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT公式 | 高機能。応答が早い | ○ | 中高生・大人 |
| Notion AI | 書いた内容の整理が得意 | △(外部接続) | レポートや下書きをまとめたい人 |
| Bing(AIチャット) | 会話しながら書ける | ○ | かんたんに使いたい人 |
| ブクログ | 読んだ本の記録ができる | × | 読書の記録をしたい人 |
| スラスラ読書 | 小学生向け。読書管理に強い | × | 本の記録をつけたい小学生 |
こうして見てみると、ChatGPTに直接感想文を書かせたいなら、やはり「ChatGPT公式」か「Bing AI」が合っています。どちらも無料で始められるのがうれしい点です。
一方で、小学生や書くのが苦手な人には「ブクログ」や「スラスラ読書」のような記録アプリが向いています。書く力を少しずつ育てたいときに役立ちます。
アプリを使うときは「何のために使いたいか」をはっきりさせましょう。AIに全部書かせるのではなく、ヒントをもらうくらいにすると、自分の力も伸ばせます。
小学生向け|ChatGPTを活用した読書感想文の始め方

小学生がChatGPTで読書感想文を作るとき、大人と一緒に使うことが大切です。AIは便利ですが、うまく使わないと「自分の考えが書けない」などの心配も出てきます。
まずは、安全に使うためのポイントを3つにまとめました。
- 親と一緒に使う
13才以下は、保護者の同意がないと使ってはいけません。一緒に使えば、内容も確認できます。 - 質問の仕方を決めておく
例えば「好きな場面を教えて」とか、「この本の主人公はどんな人?」など、決まった質問から始めましょう。 - 答えをそのまま写さない
AIの返事はヒントにして、自分の言葉に変える練習をすると効果的です。
感想文を書く流れとしては、次のようなステップがあります。
このように進めれば、AIを使いながらも、自分の言葉で感想を書けるようになります。親子で協力して進めると、学びも深まるでしょう。
中学生向け|ChatGPT活用アイデア

読書感想文を書くのが苦手な中学生でも、ChatGPTを使えばスムーズに書き出すことができます。やり方を工夫すれば、文章力も一緒に伸ばせます。
ここでは、すぐに使えるテクニックを5つ紹介します。
- テーマを考えてもらう
「この本のテーマは何ですか?」と聞くだけで、書く方向性が見えてきます。 - 主人公の気持ちを聞く
「主人公はどこで気持ちが変わった?」と聞けば、心情の変化がわかります。 - 本の中の印象的な場面を教えてもらう
「この本でいちばん大切な場面はどこ?」と質問してみましょう。 - 自分の体験に近い部分を考えてもらう
「この話と学校生活をどうつなげられる?」という聞き方も効果的です。 - 書き出しの例文を作ってもらう
最初の一文が書けると、後が楽になります。「感想文の書き出しを考えて」と伝えてみましょう。
ChatGPTは文章を全部作る道具ではありません。あくまで書くきっかけを与えるサポートツールとして活用しましょう。自分の思いと組み合わせることで、独自性のある感想文を作成しやすくなります。
高校生が気をつけたいChatGPTの使い方と落とし穴

高校生がChatGPTを使って読書感想文を書くとき、便利な反面、いくつかの落とし穴があります。特に「評価される文章」として提出する場合は注意が必要です。
まず、AIに書いてもらった文章をそのまま出すのは不正になる場合があります。学校によってはAI使用を禁止していることもあり、バレると評価が下がってしまいます。
次に大切なのは、オリジナリティです。AIが書いた文章はうまくまとまっていることが多いですが、どこか人間らしさに欠けます。感情が弱かったり、体験がないため、読んだ人の心に響きにくいです。
例えば、「この考えは本当に合っている?」とAIに聞き返すことで、より深い内容を作れます。
AIは使い方しだいで、自分の考えを広げる助けになります。ただし、使いすぎると自分の力が育ちません。あくまで参考にして、自分の表現で書くことが評価につながります。
ChatGPTを活用した読書感想文のやり方と注意点(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- ChatGPTは読書感想文の構成や書き出しのヒントになる
- 言葉の表現や言い換えの例をすぐに得られる
- 作文への苦手意識がある人でも取り組みやすくなる
- 感想文の「お手本」として活用できる
- AIに頼りすぎると自分の意見が見えなくなる
- 内容に間違いや勘違いが含まれることがある
- 学校によってはAI使用が禁止されている場合がある
- 感想文は自分の気持ちを表すものであるべき
- 良いプロンプト設計が自然な文章のカギとなる
- テーマや印象的な場面などを聞くプロンプトが効果的
- 出力された文章は自分の言葉で書き直す必要がある
- AIらしい表現は表現がかたく感情が伝わりにくい
- 書き出しと終わりは自分の言葉で整えると自然になる
- 音読して違和感を直すと文章が読みやすくなる
- 年齢や学年に合わせて使い方と工夫が異なる
.png)
-2.jpg)